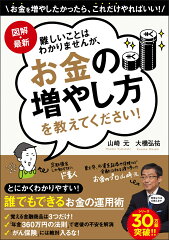2018年10月05日
神道の中今(なかいま)は悟り系の「いまここ」の意味か?~元々は続日本紀の宣命で使われた天皇即位の祝いの言葉
神道に「中今(なかいま)」という言葉があるようです。
初めて知ったのですが、ネットで調べてみると、
どうやら悟り系の「いまここ」とほとんど同じ意味であるとか。
◎「中今」の検索結果 - Yahoo!検索
https://search.yahoo.co.jp/
ふむふむ。
江戸時代の本居宣長(もとおり-のりなが)は「古事記伝」にあると言っているとか。
なるほど。
だが、ちょっと待てよ。
なんか、ひっかかる^^;
そもそも、わたくしは、こうした重要と思われる言葉や観念を見聞すると、
そそくさと調べたがる習慣があります。
いつ、誰が、どの文献で述べているのか。
そういうのを、つい調べたくなります。
たとえ、専門家が言っていても「本当かねえ」という
ひっかかりが出てくることが少なくありません。
これも、仏教の専門家が、いい加減なことを言っていたこに翻弄されたり、
戦後、左翼学者がねじ曲がった左翼史観を言い出したにも関わらず、
それを長いこと信じてしまったりして、随分と損をしたことがあるからです。
なので、学者・専門家が言ったことであっても、どこかひっかかるときは、
また重要なことは、必ず自分で文献をひもといて調べるようにしています。
で、この「中今(なかいま)」もそう。
本当かなあ、と。
で、結論からいえば「中今」は、悟り系の「いまここ」ではありません。
「古事記伝」がルーツとありましたが、これも違います。
おっと^^;
「中今」とは、天皇が即位し、位を受け継いだ時のお気持ちとお祝いの言葉です。
で、「中今」は、「続日本紀(しょくにほんぎ)」の
「宣明(せんみょう)」に初めて登場する言葉です。
【参考文献】
◎神道辞典(編:国学院大学日本文化研究所)
http://amazon.co.jp/dp/433516033X


◎続日本紀宣命(倉野憲司)


ちなみに、「続日本紀」とは、「日本書紀」に続く日本の歴史書ですね。
平安時代に、菅野真道(すがの-のまみち)が編纂したものです。
奈良時代の文武天皇から、平安時代の桓武天皇までの
約100年間の歴史を綴っています。
で、「中今」とは、「続日本紀」の「宣命(せんみょう)」で初めて使われた言葉で、
なおかつ、天皇が即位したときに、高天原から続く先祖代々の皇祖への敬意と、
自分が今、皇位を継承したことへのお祝いの言葉なわけですね。
ちなみに、宣命とは、「天皇の命(みこと)を宣(の)べる」という意味です。
つまり、天皇が即位したときのお気持ちや抱負を述べるということですね。
で、要するに「中今」とは、高天原の頃より、累々と受け継がれている天皇の位を、
「今、自分が受け継いだ(天皇の歴史の中の今)」という意味なわけですね。
事実、続日本紀には、皇位を自分が継承した意味で「中今」が使われています。
私が見つけただけでも、一番最初に出てくる
・文武天皇 即位の宣命
・聖武天皇 即位の宣命
に出てきます。
証拠として、その文面を掲載しましょう。
◎文武天皇 即位の宣命(原文)

◎文武天皇 即位の宣命(現代文)

◎聖武天皇 即位の宣命(原文)

ご覧の通りです。
文武天皇の宣明では、「高天の原に事始めて、遠天皇祖(とおすめらぎ)の御世、
中今に至るまでに、・・・」とあります。
聖武天皇の宣明では、ほぼ同じような文章で、
「遠皇祖(とおすめらぎ)の御世を始めて、中今に至るまでに、・・・」
とあります。
明らかに、歴史ある天皇家の皇位を、自分が(当時の今生天皇)を
受け継いだ意味として「中今」が使われています。
悟り系の「いまここ」ではありません。
「今この瞬間を大事にして、今を生きる」という意味ではありません。
「中今」を、悟り系の「今を生きる」「いまここ」とするのは、
もっと後世になってから登場した意味でしょう。
後世に付与されたもの。
創作されたもの。
それこそ誰が言い出したわからない、もしかすると昨今流行の悟り系に乗じて、
誰かが言い出した言葉なのかもしれませんね。
困るのは、まるで神道が、仏教やアドヴァイタと同じ「悟りの思想」を、
神道が登場した時より持っていたかのように喧伝することです。
これはなりません。
誤解を招く見解を垂れ流しかねません。
「中今」とは、「今ここを生きる(いまここ)」の意味ではありません。
今、天皇家の歴史を継承した意味です。
天皇家のバトンを、今、自分が受け継いだ(中今)ということです。
ちなみに、上記の文献「神道辞典」ページ377でも、
「中今の語を、いま現在の時を称える言葉としての意味で、(中略)、
神道の歴史観と紛らわしいニュアンスで用いることが行われるようになった」と
眉をひそめる書き方をしています。
本来の「天皇の位を受け継いだときのお気持ちの言葉」
として使われていた「中今」を、その意味と歴史を改変して使っている風潮に
チクリと刺しているわけですね。
ごもっともです。
創作といえば、神道もまた、創作されたものです。
現在の様式の神道は、奈良時代から平安時代にかけて、
密教の影響を強く受けて創作されています。
このことは、島田裕巳先生の著書にも詳しくありますね。

神道は、縄文時代から受け継がれているものではありません。
奈良時代から平安時代にかけて、仏教を元にして創作されたものです。
元々、「神道」という概念もありませんでした。
元々は、自然の中に、偉大なる生命か何か(サムシング・グレート)を
感じ続けていた慣習のような祀事です。
それは、神籬(ひもろぎ)、 磐座(いわくら)、神奈備(かんなび)といった
風習に出ていますね。
素朴な自然信仰だったわけですね。
ただ、決して劣った風習ではありません。
迷信でもありません。
偉大なるサムシンググレートを感じ続ける、
豊かな霊性と、高次の感性による素晴らしい風習、
それが、元祖神道、原始神道といってよい祀事だったわけですね。
日本が誇る、素晴らしい風習です。
が、これの「ならわし」が、後に、仏教の影響を受けて「神道」という
スタイルが作られるようになったということですね。
そういうわけでして、神道における「中今」は、
悟りとしての「今を生きる」「いまここ」ではないんですね。
「中今」とは、天皇が世継ぎを承り、代々継続している天皇の位を、
今自分が引き受けた(中今)という意味が本義なのでしょう。
悟りとしての「いまここ」は、ずっと後になってから改変され変容された意味です。
それこそ、神道は、仏教(特に密教)の影響を受けたことからも明らかなように、
禅の思想を取り入れて「中今」としたのかもしれませんね。
で、やっぱり、自分で文献などを調べる必要性を感じますね。
大雑把でも、自分で調べる習慣は、持ったほうがいいですね。

初めて知ったのですが、ネットで調べてみると、
どうやら悟り系の「いまここ」とほとんど同じ意味であるとか。
◎「中今」の検索結果 - Yahoo!検索
https://search.yahoo.co.jp/
ふむふむ。
江戸時代の本居宣長(もとおり-のりなが)は「古事記伝」にあると言っているとか。
なるほど。
だが、ちょっと待てよ。
なんか、ひっかかる^^;
そもそも、わたくしは、こうした重要と思われる言葉や観念を見聞すると、
そそくさと調べたがる習慣があります。
いつ、誰が、どの文献で述べているのか。
そういうのを、つい調べたくなります。
たとえ、専門家が言っていても「本当かねえ」という
ひっかかりが出てくることが少なくありません。
これも、仏教の専門家が、いい加減なことを言っていたこに翻弄されたり、
戦後、左翼学者がねじ曲がった左翼史観を言い出したにも関わらず、
それを長いこと信じてしまったりして、随分と損をしたことがあるからです。
なので、学者・専門家が言ったことであっても、どこかひっかかるときは、
また重要なことは、必ず自分で文献をひもといて調べるようにしています。
で、この「中今(なかいま)」もそう。
本当かなあ、と。
で、結論からいえば「中今」は、悟り系の「いまここ」ではありません。
「古事記伝」がルーツとありましたが、これも違います。
おっと^^;
「中今」とは、天皇が即位し、位を受け継いだ時のお気持ちとお祝いの言葉です。
で、「中今」は、「続日本紀(しょくにほんぎ)」の
「宣明(せんみょう)」に初めて登場する言葉です。
【参考文献】
◎神道辞典(編:国学院大学日本文化研究所)
http://amazon.co.jp/dp/433516033X

◎続日本紀宣命(倉野憲司)

ちなみに、「続日本紀」とは、「日本書紀」に続く日本の歴史書ですね。
平安時代に、菅野真道(すがの-のまみち)が編纂したものです。
奈良時代の文武天皇から、平安時代の桓武天皇までの
約100年間の歴史を綴っています。
で、「中今」とは、「続日本紀」の「宣命(せんみょう)」で初めて使われた言葉で、
なおかつ、天皇が即位したときに、高天原から続く先祖代々の皇祖への敬意と、
自分が今、皇位を継承したことへのお祝いの言葉なわけですね。
ちなみに、宣命とは、「天皇の命(みこと)を宣(の)べる」という意味です。
つまり、天皇が即位したときのお気持ちや抱負を述べるということですね。
で、要するに「中今」とは、高天原の頃より、累々と受け継がれている天皇の位を、
「今、自分が受け継いだ(天皇の歴史の中の今)」という意味なわけですね。
事実、続日本紀には、皇位を自分が継承した意味で「中今」が使われています。
私が見つけただけでも、一番最初に出てくる
・文武天皇 即位の宣命
・聖武天皇 即位の宣命
に出てきます。
証拠として、その文面を掲載しましょう。
◎文武天皇 即位の宣命(原文)

◎文武天皇 即位の宣命(現代文)

◎聖武天皇 即位の宣命(原文)

ご覧の通りです。
文武天皇の宣明では、「高天の原に事始めて、遠天皇祖(とおすめらぎ)の御世、
中今に至るまでに、・・・」とあります。
聖武天皇の宣明では、ほぼ同じような文章で、
「遠皇祖(とおすめらぎ)の御世を始めて、中今に至るまでに、・・・」
とあります。
明らかに、歴史ある天皇家の皇位を、自分が(当時の今生天皇)を
受け継いだ意味として「中今」が使われています。
悟り系の「いまここ」ではありません。
「今この瞬間を大事にして、今を生きる」という意味ではありません。
「中今」を、悟り系の「今を生きる」「いまここ」とするのは、
もっと後世になってから登場した意味でしょう。
後世に付与されたもの。
創作されたもの。
それこそ誰が言い出したわからない、もしかすると昨今流行の悟り系に乗じて、
誰かが言い出した言葉なのかもしれませんね。
困るのは、まるで神道が、仏教やアドヴァイタと同じ「悟りの思想」を、
神道が登場した時より持っていたかのように喧伝することです。
これはなりません。
誤解を招く見解を垂れ流しかねません。
「中今」とは、「今ここを生きる(いまここ)」の意味ではありません。
今、天皇家の歴史を継承した意味です。
天皇家のバトンを、今、自分が受け継いだ(中今)ということです。
ちなみに、上記の文献「神道辞典」ページ377でも、
「中今の語を、いま現在の時を称える言葉としての意味で、(中略)、
神道の歴史観と紛らわしいニュアンスで用いることが行われるようになった」と
眉をひそめる書き方をしています。
本来の「天皇の位を受け継いだときのお気持ちの言葉」
として使われていた「中今」を、その意味と歴史を改変して使っている風潮に
チクリと刺しているわけですね。
ごもっともです。
創作といえば、神道もまた、創作されたものです。
現在の様式の神道は、奈良時代から平安時代にかけて、
密教の影響を強く受けて創作されています。
このことは、島田裕巳先生の著書にも詳しくありますね。

神道は、縄文時代から受け継がれているものではありません。
奈良時代から平安時代にかけて、仏教を元にして創作されたものです。
元々、「神道」という概念もありませんでした。
元々は、自然の中に、偉大なる生命か何か(サムシング・グレート)を
感じ続けていた慣習のような祀事です。
それは、神籬(ひもろぎ)、 磐座(いわくら)、神奈備(かんなび)といった
風習に出ていますね。
素朴な自然信仰だったわけですね。
ただ、決して劣った風習ではありません。
迷信でもありません。
偉大なるサムシンググレートを感じ続ける、
豊かな霊性と、高次の感性による素晴らしい風習、
それが、元祖神道、原始神道といってよい祀事だったわけですね。
日本が誇る、素晴らしい風習です。
が、これの「ならわし」が、後に、仏教の影響を受けて「神道」という
スタイルが作られるようになったということですね。
そういうわけでして、神道における「中今」は、
悟りとしての「今を生きる」「いまここ」ではないんですね。
「中今」とは、天皇が世継ぎを承り、代々継続している天皇の位を、
今自分が引き受けた(中今)という意味が本義なのでしょう。
悟りとしての「いまここ」は、ずっと後になってから改変され変容された意味です。
それこそ、神道は、仏教(特に密教)の影響を受けたことからも明らかなように、
禅の思想を取り入れて「中今」としたのかもしれませんね。
で、やっぱり、自分で文献などを調べる必要性を感じますね。
大雑把でも、自分で調べる習慣は、持ったほうがいいですね。

Posted by トリステーザ@ at 22:59
│神社・神道